- 現在の相場は“過熱寄り”。長期的には9〜18か月(〜2026年中)は持続しやすいが、5〜10%の押し目を何度か挟む想定が現実的。
- 冷め方は2タイプ:①ショック型(ドンと一気)、②ファンダ型(じわじわ)。
- 基準確率の目安:じわじわ 65%、一気 35%。ただし「信用・流動性スイッチ」が入ると比率は逆転しうる。
- 見極めは信用と流動性のシグナルが要。HY OAS、NFCI、VIX、FRA-OISなどを“閾値つき”で監視。
目次
目次
- なぜいま「過熱寄り」に見えるのか
- 冷め方は2パターン:ショック型 vs ファンダ型
- 歴史的な実例で学ぶ「一気」と「じわじわ」
- いまの相場に当てはめる確率見立て(65% : 35% の根拠)
- スイッチ指標と閾値:一気に傾く“引き金”を可視化
- 行動指針:過熱が続くとき/終わるとき
- よくある誤解と落とし穴(FAQ)
- まとめ:結論と当面の運用テンプレ
1. なぜいま「過熱寄り」に見えるのか
- 金融条件が緩い:金融環境指数(NFCIなど)がマイナス圏=流動性が潤沢。
- 信用がタイト:米ハイイールド債のスプレッド(HY OAS)が歴史的に低いゾーン=資金調達が容易。
- 高バリュエーション:S&P500のフォワードP/Eが5年・10年平均を上回る水準。
- テーマ集中:AI・メガテックに資金が集中。指数の集中度が高く、上昇圧力も調整の脆さも増幅。
読み:緩い条件が続くかぎり“熱”は残りやすい。ただし集中相場の副作用として、個別ショックが起きた場合の波及スピードは速い。
2. 冷め方は2パターン:ショック型 vs ファンダ型
| 型 | きっかけ | 下げ方 | 期間感 | 代表的サイン |
|---|---|---|---|---|
| ショック型(一気) | 流動性・信用ショック/政策サプライズ(規制・関税・制裁等) | 短期間に急落、ギャップダウンも | 数日〜数週間で最初の−10〜20% | VIX急騰、HY OAS急拡大、FRA-OIS急拡大、NFCIの急悪化 |
| ファンダ型(じわじわ) | 実質金利上昇、増益鈍化、P/E圧縮 | 戻り売りを挟みながら階段状に下落 | 数か月〜年単位 | バリュの徐々な縮小、ガイダンス下方修正、出来高の枯れ |
3. 歴史的な実例で学ぶ「一気」と「じわじわ」
- 一気の典型:
- 1987年「ブラックマンデー」:米株が1日で−22.6%。
- 2020年 初動:コロナ不確実性で数週間の急落、VIXが80超。
- じわじわの典型:
- 2000–2002年 ドットコム崩壊:年単位でP/E圧縮、NASDAQは累計**−78%**。
- 2007–2008年(リーマン前まで):高値から約11か月、−20%弱のなだらかな下落→その後ショックで加速。
- 1966–1982年 米国の世俗的弱気:16年かけて実質で大きく目減り。
- 日本の1990年代以降:「長い滑り台」=過熱解消とバランスシート調整が年単位で継続。
ポイント:「最初から必ず一気」ではない。むしろじわじわ始まって→途中でショックが重なり一気に見える、という順番が珍しくない。
4. いまの相場に当てはめる確率見立て
- ベース:じわじわ 65%
- 理由:金融条件が緩い/信用がタイト/業績はまだ下支え → **“高止まり→徐々に圧縮”**になりやすい。
- テール:一気 35%
- 理由:集中相場ゆえ個別大型ショックが起こると流動性が薄いところから連鎖しやすい(証拠金引き上げ→売り連鎖)。
※この比率は**“シグナルの悪化”でダイナミックに動く前提です。固定値ではなく運用上の初期パラメータ**と考えてください。
5. スイッチ指標と“閾値”——確率が一気に傾く引き金
信用・流動性
- HY OAS(米ハイイールド・スプレッド):
- 目安:4%超へ短期間で拡大 → リスク再価格付けのサイン。
- FRA–OIS(短期資金調達ストレス):
- 目安:数日〜数週で**+30〜50bp**級の拡大 → 資金繰り悪化の先行。
- NFCI(金融環境):
- 目安:0へ接近/上抜け → 緩さの剥落。
ボラティリティ
- VIX:
- 目安:数日で+15pt級の急騰・25超の定着 → 価格調整の加速に注意。
センチメント・フロー
- 株式ETF/投信の資金流出転化、マージンデット(証拠金債務)の減速/逆回転、大型銘柄のブレッドスプレッドの悪化など。
6. 行動指針:過熱が続くとき/終わるとき
6.1 続く(延命)シナリオの戦い方
- 基本:押し目買いは**5–10%**を目安に段階的。
- 分散:指数集中の副作用対策にセクター分散/サイズ分散。
- リスク管理:
- 逆指値・トレーリングストップを銘柄の歴史的ボラに合わせて設定。
- 現金比率レンジ(例:10–25%)を事前定義して自動で再均衡。
- ヘッジ:イベント期(決算・政策)だけ短期のボラ買いや相関の低い資産でオーバーヘッジ。
6.2 終わる(冷却)シナリオの身のこなし
- トリガーベースで段階的に軽くする:
- 例)HY OAS **>3.5%で現金+5%、>4.0%**でさらに+5%…
- VIX >25定着でネットエクスポージャーを低減、デュレーション短縮。
- 個別:稼ぎ頭(含み益大)の先行利確→広がる前に火元を断つ。
- ルール化:ヒヤリ・ハットを“人の裁量”にしない(事前にIf-Thenを書面化)。
7. よくある誤解と落とし穴(FAQ)
Q1. ショックは毎回“突然”?
A. 価格は突然でも、信用・流動性指標は事前に悪化することが多い。FRA–OIS、HY OAS、VIX、NFCIを“セット”で見る。
Q2. バリュエーションが高い=すぐ崩れる?
A. 流動性が潤沢なら“高止まり”が延命し得る。崩れるのは流動性・信用が変調してからが多い。
Q3. 今から全部現金に?
A. 二者択一は非効率。トリガー連動の段階調整と分散+ヘッジで“上にも下にも”対応できる設計に。
Q4. 金(ゴールド)は?
A. 実質金利・ドル・中銀需要の影響が大。株の急落期に守ってくれる保証はないが、分散としては依然有効。
8. まとめ:結論と当面の運用テンプレ
- 結論:
- 冷め方は両方あるが、現状はじわじわ 65%:一気 35%。
- ただし信用・流動性スイッチ(HY OAS、FRA–OIS、NFCI、VIX)が入れば一気に傾く。
- 長期軸では**〜2026年**まで“過熱寄りが持続”しやすいが、押し目やミニショックは織り込む。
- 当面のテンプレ(例)
- 平時:押し目(5–10%)を段階買い。集中リスクを分散で薄める。
- 警戒:VIX >25 or HY OAS >3.5%でリスク10–20%削減。
- 非常:HY OAS >4%か、FRA–OISが+30–50bp急拡大 → 一気モードと判断、ネットエクスポージャーを大幅縮小、ヘッジ強化。
- 再評価:指標が落ち着けば段階的に回復(ルールで“戻す勇気”も確保)。
注:上記は投資助言ではなく、意思決定の枠組みです。指標の算出方法・遅延・改定に留意し、運用ルールはご自身の許容ドローダウンと投資期間に合わせて調整してください。
(基準日:2025年10月13日 JST)







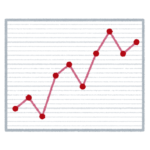
最近のコメント